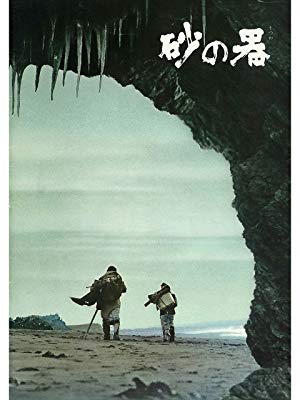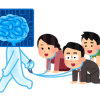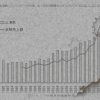AmazonPrimeにてふと目に留まり視聴。原作(松本清張)があることだけは知っていたが、一切の予備知識がないまま唐突に見始めた。本作は映画にとどまらず幾度もテレビドラマ化されていることを視聴後に知って驚く。なんと5回。近年では2011年に制作。
視聴し始めてすぐに、私は古い日本の風景に惹かれた。フィクションとはいえ当時のロケ地の空気が映っていた。「貴重な写真を覗き込む」ような感覚で映画を見ていた。
自動車が見慣れないデザインであったり、携帯も当然ない。電話交換手が出てきたりする。また、夏の暑さを強調する演技や演出がたくさんあるが、警察署内などで冷房が無いことも伺える。おそらく電車内も冷房はない。現代との違いは大変興味深いものだった。
確かに東京の街角の風景は古臭くはあるのだが、一方で「かなり現代的だな」という印象も強い。当時は戦後30年足らずという時代なのだが、もう今に通じる空気がそこにはあった。
田舎の風景も数多く登場する。こちらは私にとってはやや現実感がない。山間の村やその駅舎、交番などの造形は、明治や大正時代にまで遡りかねない佇まいである。「時代劇」くらいの異世界感はある。
様々な風景が映し出されるたびに、今(2018年)から40年以上前の日本の姿に意味もなく、ただただ感心していた。秘境のような田舎から、東京の暑苦しくゴミゴミした街角ですら美しく見えたのは何の偏見だろうか。よくわからない不思議な気分だった。
さてここで、映画の感想を率直に述べれば「物語の内容に引き込まれることはなかった」となる。前半の捜査過程はなかなか面白いだけに少し残念だ。
この映画を正面から楽しむためには、現代では既に失われている「常識」が必要だと感じた。見た目の変化はわかるが、一般常識や社会通念のような心理面の変化は、見ただけでは分かりづらい。この映画を見る上で重要な何かが、今では転換している気がした。時代によっては当然と思われていることが、別の時代では跡形もない。そんな違いがあるはずだ。
そう思わせた一番の違和感は、容疑者の犯行動機である。殺人へと至る機微が作品内であまり明瞭には説明されない。「説明がなくても当然わかるであろう」ということになっている。重く苦しい事情があることは懇切丁寧に説明されるのだが、殺人にまで至る感覚が最後まで掴めない。「全くわからない」ということではないのだが、「殺してしまうほどのことなのか?」と終始疑問符がついて回る。
少し言い換えると、犯人はもとより、そこに登場する人物全員が、現代の感覚からすると真面目すぎるのだ。「それほど一本道で思い詰める必要があるのか」と問いたくなるのである。「らい病の親を持つ」ことが巡り巡って殺意にまで昇華する過程を、想像することはできても、当時の差別と偏見の程度や感覚が肌身に感じられない今となっては、少々掴みにくい。
遺伝や感染力や治癒への誤解から、一家ごと迫害を受けることなどは理解ができるのだが、「地域や社会でどれほどタブー視されているのか」などは想像しにくい。逆に映画を見ることで、「らい病の親を持つことは殺人を犯すほどの窮地にある」という構図を「学んで」しまうのだ。これではミステリーとしてのカラクリとして成立しにくい。
さて、自分の想像力の無さに呆れるわけだが、もっと言えば現代の感覚だと「難病の親の子」という状況は、むしろ音楽家としての人気を後押しする要素になるのではと、打算的に考えることすらできてしまう。実際に現代はそういう回り方をしている。
難病の親と幼いときに生き別れ、再開を果たして世話をしながら音楽活動をする。そんな才能のある若者がいたら、現代ではメディアと世間がこすり倒すほどに食いつく格好の美談となってしまうだろう。当時と今の世間の全体の共通感覚に大きなズレがある。病気に関する知識もそうだが、それ以外の空気感もだいぶ異なる。
途中、乞食をする親子の描写がある。「らい病を患った者が家と故郷を捨て、子と共に全国の辺境各地(おそらく石川~島根の日本海側沿岸)を転々としながら放浪し、野宿でいくつかの季節を過ごす」という下りだ。容疑者の幼少期ということで、当然時代は遡っているが、ここはまさに時代劇の様相となっている。「放浪らい」と呼称するらしいが、私には想像の外の話である。都会で温々育った私にはファンタジー世界に近い。戦前のド田舎の風景はファンタジー作品のような美しさと過酷さを感じることができる。
それこそファンタジー作品であれば「そんな事もあったのか」と理解することはできる。しかし犯行動機や重要な心象として「なるほど」と素直に飲み込むことは少々難しい。ミステリー作品であるために、こちらもつい力んで説得力を求めてしまう節がある。私が勉強不足な上に想像力を欠いているのが悪いのだが、やはり学ばされてしまうだけなのである。
少なくとも当時は現実的で説得力のまだあったプロットが、今ではその力を失いかけている。そうなってしまうとミステリーとしての力強さが損なわれ、少々突飛だったり、場合によっては都合が良すぎる話に見えてしまうこともあるだろう。「島根から子供が家出をして大阪で拾われて育てられる」や「戸籍が変更され家族が入れ替わっている」なども、当時と今では必然性や現実感に大きな差があるはずだ。
大小様々な共通感覚が今と当時で違い、現代的な感覚で呑気に見ていると少しずつ違和感となって蓄積してしまう。この違和感の正体は物語の不備というわけではなく、私の学や見識の無さからくるものと言えるし、自己弁護するならば時代による背景や常識の変化と言うことになる。ある意味では、社会がより良い方向へ進んだ結果、代償として「砂の器」の面白さがどこかへ消えたといえる。
TV版でリメイクされるたびに「らい病」の設定が丸ごと変更されるのは、病気に対する配慮もあるだろうが、社会全体の変化によって私のような人間には物語がわかりにくくなってしまったことも大きいだろう。
病や戦争などと直接関連しない部分でも気になった点はある。一番の不明点は「証拠隠滅の手法」だ。率直に言えば不可解極まりない。ドラマチックでありロマンチックであるのはわかるのだが、燃やせば済む話をどうしてあのような手法となったのか。
後の顛末も含めて「華のある」下りで、小説映え、ひいては映像映えするのはわかるが、犯人の行動としては「工夫している割にずさんさが目立つ」というアンバランスなものである。当時はこれが許容されるような背景があったのだろうか。この辺りはもう私にはわからない。
例えば、「刑事などいないのに、列車内で勝手に追われていると勘違いして焦り、証拠品を急遽車窓からばらまく」などであれば理解がしやすい。ただこのような指摘は偏屈な素人の思いつきにすぎない。素人の注文を聞き入れていると、作品自体が壊滅する類の「センスのない意見」なのだろう。
もう一つ。「紙吹雪の新聞記事」「記者」「刑事」「撒いた当人」の邂逅も、なかなか都合のいい偶然の連続で構成されている。そういう数奇な巡り合わせは、現実世界ではしょっちゅう起きていることではあるが、現代のフィクションでは、たとえ偶然だとしてももう少し丁寧に必然性を考慮するだろう。
細かいことをネチネチ書いてはいるが、面白くなかったわけではない。大変面白かったのだ。というのも、次第に私は「この映画に素直に引き込まれない理由がどこにあるのか」と考え始めていた。どのような共通感覚や時代背景の違いによって、私は違和感を感じてしまうのか。そこに興味の中心が移っていった。日本の近代から現代へのつなぎ目を肌で感じるために、資料的な側面を主眼に置いてこの映画を捉えようとしていた。
当時の「戦争」との距離の近さは私にとって特に興味深かった。原作が書かれたのが1960年(昭和35年)で戦後15年ということになる。書かれた当時はたった15年しか経っていない。従って、登場人物の生い立ちなどが語られれば、当然のように戦前が出てくるし、物語のキーとなる過去の出来事が戦中、戦争直後(昭和20年前後)となっていたりするのに何の不思議もない。今、現代劇でこれをやろうとすると、遡るためには祖父では足りなくなってきている。曽祖父まで遡る必要がある。これはだいぶ遠い。
映画の制作自体は1974年(昭和49年)で、戦争終結から29年ほどとなる(ちなみに今年2018年は戦後73年)。物語の節々に戦争がまだまだ身近だったことが伝わってくる。この時代だと、仕事ざかりの中年くらいなら全員が戦争を体験していることになる。物語の中のキャラクターだけではなく、見ている方もほとんど皆戦争を体験しているはずだ。なにより俳優自身が「実際に」第二次世界大戦を体験しているという「戦争との近さ」について説明不要の共通感覚がある。ところが私達にはそのような体験はない。直接話を聞いたことすらもない。注意深く見ていないと感じ取ることも出来ない。
「古いながらも現実感のある近代的な東京」と、その中で地続きで語られる「私にとっては全く現実感のない戦争」のシームレスな結合に、今とは異なる常識がそこにあったことを予感させられる。
私にとってこの映画の見どころは、「戦後30年ほどの昭和の日本の風景と人々」ということになる。東京は既に現代的でありながら、田舎はまだまだ戦前の色を残しつつ、「ついさっきまで戦争があった」というクロスオーバーした時代を感じ取れる作品だ。もう一つ見どころとして付け加えるならば、「丹波哲郎氏の好演」か。
自分勝手な窮屈な見方をしてしまったが、面白い映画であることは間違いない。Amazonレビューの評価は少々高すぎるような気もするが、当時の時代の空気を今に伝える素晴らしい作品だ。