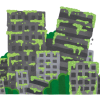授業が終わると教室は急に開放的な雰囲気となった。ゴソゴソと部活の準備をしていると形嶋が俺を呼ぶ。形嶋美咲とは出身の小学校は違ったが、気づけば早々に友人となったうちの一人だ。どちらかと言えば威勢のいい彼女だが、今日のその声は少しか細い。同じクラスであるのにわざわざ廊下から呼んでいるのも変だ。この時点で違和感はあった。
俺は教室の窓側で白い靴下を膝上までビンビンに伸ばしていた。「はいはい。オーケー待ってくれ。野球部は靴下を履くのが面倒なんだ」と、ユニフォームに着替えながら誰にも聞こえない独り言を調子よく呟いていた。形嶋の声にいつもと違う「気の弱さ」を感じ取り、そこそこ深刻な頼み事だろうとは予想がついた。少なくとも「バドミントンのシャトルが防護ネットに引っ掛かったから取れ」や「倉庫の扉が重いから手伝え」のような野暮用ではないことは分かった。
俺は「忙しいんだ」と言わんばかりに勿体つけて、ゆっくりと振り向いた。振り向きかけた時、視界ギリギリに夏用の制服を着た二人が映る。廊下の対岸の掲示板にもたれながら俺を呼ぶ形嶋と、その隣で神妙な顔をしてうつむいている浮田だった。あと何か持っていたような気がするが、慌てて視線を切ったのでよく見えなかった。
思っていたよりずっと普通じゃない。
一瞬でアイツらがやろうとしていることは分かった。先日、慎之介から「浮田はお前が好きらしいぞ」とリークがあったばかりだったからだ。慎之介は「爪楊枝でも口にくわえてんのか」というような下町風情のやんちゃな半笑いを浮かべて寄ってきて、勢いよく俺の肩をバンバン叩き、それだけを告げて早々に立ち去っていったのだった。この時はこんなにクリティカルな情報が唐突に漏洩するとも思えず、信憑性はかなり低いと勝手に見積もっていた。情報屋気取りの慎之介の思いつきだろう。そう思っていた。
浮田藍子はバレーボール部に所属していて、見た目はショートカットでボーイッシュだが、内面は形嶋とは逆で比較的おとなしい。だからと言って無口というわけでもなく、話せば感じのいいやつでもあった。先月まで俺と浮田は隣の席で、毎日くだらない冗談を言っては二人で笑っていた。確かに楽しかったし、席替えになったときは少し寂しかったかもしれない。とはいえ浮田に対して特別な感情は持っておらず、自分の中ではそれらはパラパラ漫画のひとコマにすぎなかった。記憶に留まることのない穏やかな日常でしかなかった。
浮田は他の誰かにとっては可愛らしいのかもしれない。しかし俺は、別のクラスで面識すらない石坂ひとみに心のすべてを奪われていた。最近は行き過ぎた敬虔な教徒のように、日常のすべてを石坂と関連付けて物を考えていた。石坂を毎日遠目で見かけては心躍らせ、いつか廊下で「どうにか正面衝突でもしないか」と、気持ち悪いながらもささやかな妄想を膨らませていたのだった。「なんで俺は石坂と同じクラスじゃないんだ」とため息をついては、事あるごとにお手軽な悲劇の主人公になりきっていた。どうにも納得ができなかったのは、同じマンションに住む小学校からの仲だったハルカが、石坂と同じクラスになっていたことだ。俺と替われや。毎晩そう思っていた。
ハルカと俺は住んでいる階まで同じで、小学校低学年の頃は家族ぐるみでキャンプにもよく行っていた。今でも家族間の交流は多く、それなりに気心知れた仲ではあるのだが、「鼻につくマセた女子選手権」があればぶっちぎりで優勝するような奴でもあった。口喧嘩になれば勝ち目はなく、暴力に訴えようにも母親同士の中が異様なほど良いため、妙な真似は出来ないということは幼少期からの訓練により学習済みだった。全ての情報がハルカとハルカの母親を介して自分の母親にまで筒抜けになってしまうのだ。
それでも俺は「最悪お前とのツーショットでもいいから石坂の写真を頼む」と、ハルカに恥も外聞もなくお願いするほどだった。「最悪とはなんだ」と憤慨しながらも、先の慎之介と似たようなニヤニヤ顔を浮かべて二つ返事で引き受けてくれた。ハルカは去り際に「軽く舌を出しながら敬礼する」という難度の高い技をキメていた。馬鹿にしているのは明らかで、無性に腹が立ち、「気持ち悪っ」と言いかけていた。しかし、今従うべきボスは間違いなくハルカであったし、「石坂の写真が手に入るかもしれない」という圧倒的な高揚感の前に、不覚にも俺は随分とノリの良い愛想笑いをカマしていた。
後日「KくんとTとO先輩の写真よろしくね」というふざけた一文とともに、律儀に写真は送られてきた。その写真は、石坂とその友達がフードコートらしき場所で何か飲んでいるというものだった。俺は初めて見る私服の石坂に、何故か神聖性を感じてしまい「写真を見るだけでも汚してしまうのではないか」という中学生男子特有の高貴な童貞力を発揮していた。
「ーーー」
俺はもう一度形嶋から呼ばれていた。改めて形嶋と浮田の存在を背中に感じて、あっという間に打ち上げ花火のような迫力で心臓が鼓動し始めていた。
俺がとっさに取った行動はなかなか最低なものだった。「呼ぶ声など聞こえていない」という素振りで、隣で部活の準備をしている悠太に襲いかかったのだ。誤魔化したいというその一心で、無理矢理プロレス技をかけにいっていた。それまで熱心に内野手用のグラブにオイルを塗り込んでいた悠太は2秒後に叫んでいた。
「ああ?んん!おい。イデデデデ!!!」
「『意中ではない仲の良い異性』から好意を伝えられる」という味わったことのない緊迫感に、対峙できる度胸や真摯さなどなく、惨めにも逃げ出してしまったのだ。この「逃げ」は浮田に対する気遣いなどではなく、単に自分のエゴに他ならない。彼がそれを理解出来するにはもう少し時間が必要だった。
この弱々しい彼、すなわち自分をもし擁護してあげるのならば「つい数ヶ月前まで小学生だった現役バリバリのクソガキがこんな状況に耐えられはずもない」となるだろう。石坂を絶対神とした奇妙なまでの忠誠心と、己の懐の浅さが、自分勝手にも逃げ場のない状況を作り上げていた。彼が少しでも大人であれば、責任を持って丁寧に断ることも出来ただろうし、逆に何の恋愛感情も持たずに性的好奇心のみで、無責任にも浮田と付き合い始めることだって出来ただろう。
既に悠太の奇声を合図に教室の隅でプロレスショーの幕が上がっていた。何の前フリもなく、いきなりクライマックスを迎えたじゃれ合いに、形嶋は呆気にとられていた。「靴下片方野郎」となった俺と「グラブ油野郎」となった悠太との無観客試合は、永遠に続くかのような神々しささえ放っていた。その激しい技の応酬の合間、浮田が形嶋の半袖の縁を掴んで後ずさりしていたのが見えた。「もう帰ろう」とでも言いたげだった。俺はホッとすると同時に、急に大きな喪失感を感じ始めていた。
なんだこれは。
せっかくの好意を卑怯な手段で逃げているのに、その好意が消えそうになると途端に「寂しい」と感じていたのだ。プロレスをして無視を決め込んでいながら、どこかで「帰らないでくれ」「嫌いにならないでほしい」と願っている。随分な心理状態じゃないか。
クソガキとはいえ流石に道理がおかしいことには気付く。正確に言葉を選ぶなら「気付いた」と言うよりも「発狂」に近い。一気に押し寄せた複数の感情が洪水となって身体中を飛び跳ねる。「今すぐ地球は俺の足元から真っ二つに割れてくれ!」と馬鹿らしい現実逃避を持ち出して、なんとか自分の身に起きている全てを薄めようとしていた。地球が割れないなら全身全霊をかけてプロレスへ没頭するしかないじゃないか。俺は夢中でプロレスをしていないと死んでしまう生き物になっていた。
相変わらず形嶋は近寄ってはこない。その後も2度3度俺を呼んでいたが、声のトーンは更に弱々しいものになっていた。しばらく呼ばれない時間が続いたので、チラリと廊下に目をやると、人影はもうなかった。それを確認してから悠太を思いっきり突き飛ばして、俺はゼェゼェ肩で息をしながら大の字になって倒れ込んだ。すかさずマウントを取ろうと寄って来た悠太に、なんとか呼吸を整えながら絞るように言った。
「…った。まった。おしまいおしまい。試合、終了」
プロレスのほかに何か別の物も終わっていた。
「形嶋が呼んでたぞ、いいのかあれ」
真っ白なユニフォーム姿の悠太も息を切らしながら下を向いて言う。膝に片手を付いて中腰になったまま、誰もいない廊下をもう片方で指さした。俺は仰向けのまま呼吸するのが精一杯だった。
好意の呼びかけだったはずの形嶋と浮田を完全に無視したという罪悪感。そのジットリとした後悔とは裏腹に、プロレスによってさらに最高潮に達した脈拍と意味不明なテンション。これらが何度も体内で対消滅と対生成を繰り返していた。気づけば明かりの点いていない蛍光灯を「単に視界に入っていた」というだけの理由で呆然と眺めていた。寸分違わず等間隔に配置された教室の蛍光灯は、次第に俺の呼吸と動揺を収めていった。
「当番だから、先行ってるよ」
悠太はそう言って、内野ゴロをさばく動作をしながら教室を出ていった。
校舎全体に様々な楽器の音色が脈絡なくバラバラに流れている。吹奏楽部の練習だ。これは他の部活にとって開始の合図のようなものだった。ようやく立ち上がって外を見ると、陸上部がグラウンドに水を撒いている。テニス部員は話しながら仕切り用のフェンスを重そうに引きずっていた。「ザザザザ、ザザザ」といつもの聞き慣れた音だ。誰も彼も暑そうにしている。梅雨明けは未だ明言されていないものの、事実上すでに真夏が到来していて、太陽の位置はこれでもかと高かった。
悠太のせいで油臭くなっていた手で、もう片方の靴下を慌てて履く。かなりの大遅刻を覚悟していたが意外にもまだ時間に余裕があった。「これ、動いてんのか」と思うほど教室の時計は悠長に時を刻んでいた。
「よし」
準備ができた。野球帽をグリグリと深くかぶり直す。頭が締め付けられる感覚が今はなぜか心地良い。スパイクの入った袋とグラブを脇に抱え、上履きをだらしなくつっかけてカパカパ鳴らしながら教室を出た。ふと忘れ物がないかと気になり、呼び止められるように教室を振り返る。さっきまでの台風のような出来事などまるでなかったかのように、無人となった教室は静まり返っていた。いやいや、忘れ物なんてない。ここで起きていたことが何だったのかを、少しの時間でいいから見渡したかった。
そこには確かに、かけがえのない人生のひとコマとしての余韻があった。誰もいなくなったガランとした空間は、妙な名残惜しさをたたえていた。

本稿は「アイラブユー・ゲーム」を読んで面白かったので影響されて書いたものです。フィクションです。