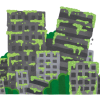いつからだろうか。私は春の嵐のたびにこの日を思い出す。
新しいクラスメイトと打ち解け始めていたある日、これから給食の時間だというのに外が随分と暗い。「今日で世界が終わるぞ」と父親にでも真顔で言われたら、信じてしまいそうな暗さだった。ブワンという風の音と共に、何度もベチベチベチと窓に雨がしなる。教室からは、届きそうなほどの低い雨雲が、氾濫した川のように流れているのが見える。5月の嵐だった。
廊下へ出ると、湿った生暖かい強風と雨粒が雑に吹き込んでいる。なにやら興奮気味の他のクラスの生徒達が、迷い込んだ風と競争するように走り抜けていた。振り返ると外の暗さのせいで、教室の蛍光灯が妙に眩しい。まるで夜だ。そしてまた熱風のような空気の塊が、私の髪をなびかせて突き抜けた。
校舎の中へとなだれ込んだその気流は、子どもたちの歓声がこだまする長い廊下を力任せに通り、そこら中に張り出されている展示物や紙をパタパタと鳴らし、ずっと向こうに小さく見える、体育館へと繋がる吹きさらしの渡り廊下に押し寄せて、外の空気と混じってどこかへ消えた。
生まれて初めて情緒的な感情を抱いた瞬間だったかもしれない。この時私は春の嵐の匂いを自覚したのだった。そしてただ「生きている」というだけの理由で、まったく根拠のない自信と希望が、少年のカラダ全体に広がっていった。
大人になって振り返れば、この自信と希望にはある種のジレンマがあるのに気づく。風や雨音、薄暗さや湿度を感じとる身体と、それに呼応する感情は、自分が確かに生きていた証として、何物にも代えがたい非常に強力な証拠となる。しかし一方で、他人への提出が不可能な、極めて主観的な体験にすぎないという致命的な脆さがある。誰とも共有することはできず、私が死ねば全て無に帰すほかなく、うたた寝で見た夢とさして変わりがない。
子供であった私は、恐らくこの儚さを無自覚的に察知し、そこにある種の大人っぽさを自覚して、暗い廊下の途中で一人佇み、酔いしれたのだった。
今思えばこの春の嵐は、人より早い思春期の到来を、わざわざ大げさに告げに来る役目だったのかもしれない。ほかに何人の子供に通告して回ったのだろうか。嵐は、年頃の少年少女を見つけては風を送り込み、荘厳な高笑いを撒き散らして、私の住む地域を優雅に通り抜けていった。